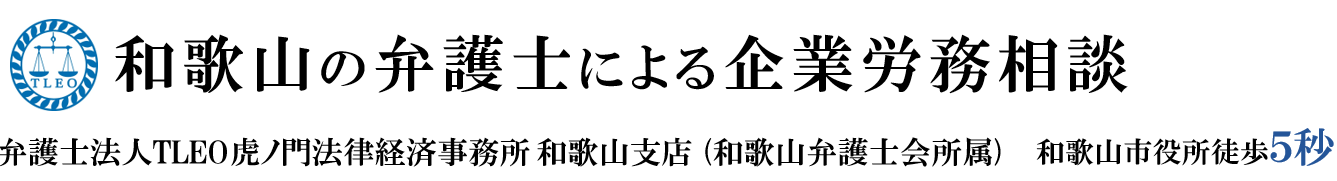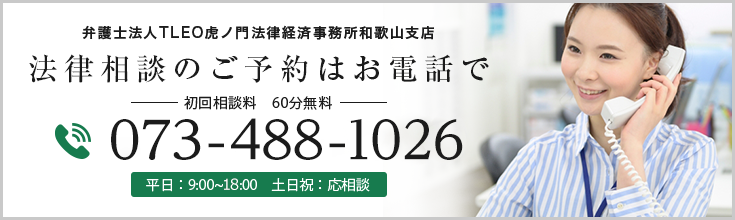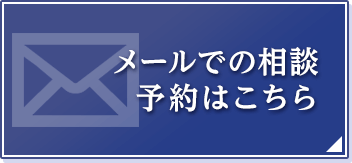【弁護士解説】退職者からの残業代請求対応法
残業代請求とは何か
退職した元従業員(の代理人弁護士)から、ある日突然、内容証明郵便で未払い残業代を請求する通知が届く、というケースは、残念ながら多くの企業で起こりうる問題です。特に近年、労働者の権利意識の高まりや法改正の影響もあるようで、当事務所でも実感として、経営者の皆様から「未払い残業代請求をされた」とご相談いただくことが増加しています。
経営者の皆様にとって、このような請求は、まさに青天の霹靂で戸惑ってしまうかもしれませんが、感情的に対応したり、安易に要求に応じたりするのは禁物です。まずは残業代請求の基本的な仕組みを正しく理解し、冷静かつ適切に対応することが会社を守るための第一歩となります。
残業代請求の基本的な仕組み
労働基準法(第32条)では、労働時間の上限が原則として「1日8時間、1週40時間」(※1)と定められています(これを「法定労働時間」といいます)。そして、会社が従業員にこの時間を超えて労働(時間外労働や休日労働)をさせるためには、まず労働組合または労働者の過半数代表者との間で「時間外労働・休日労働に関する協定(通称:36協定《サブロク協定》)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。しかし、36協定を締結していたとしても、残業代の支払義務が免除されるものではありません。実際に残業が発生した場合には、通常の賃金に25%以上の割増を加えた賃金を支払う必要があり、さらに、深夜(22時〜翌5時)や休日に働かせた場合には、より高い割増率が適用されます。そのため、適切な手続きを踏まずに残業をさせていた場合や、割増賃金の計算が不正確だった場合には、退職後であっても未払い残業代として請求される可能性が高くなります。
※1:原則として「1日8時間、週40時間」について
常時10人未満の労働者を使用する「商業・映画演劇業(映画の製作の事業を除く。)・保健衛生業・接客娯楽業」の事業場の場合は特例措置として、「1日8時間、週44時間」まで認められたり(労働基準法施行規則第25条の2)、変形労働時間制を導入することで「1日10時間」まで認められるなど一部例外があります。
なぜ退職後でも請求されるのか?
労働基準法に基づく残業代請求権は、退職によって消滅するものではないからです。むしろ、在職中は会社との関係を考慮して請求を控えていた従業員が、退職を機に弁護士に相談し、まとめて請求してくるケースの方が多いです(※2)。また、労働者側の代理人となる弁護士事務所が、SNSや広告などを通じて「退職後の残業代請求ができる」と積極的に情報発信をしている現状も影響しています。このような背景から、退職時に「お疲れさまでした」で済ませるのではなく、在職中から労働条件について適切に管理しておくことが重要です。
※2:残業代請求の多様化について
従来は、「退職した従業員が、単独で、弁護士を通して請求してくる」ことが多かったのですが、最近は【在職型】(在職中の請求)、【集団型】(複数人による同時請求)、【本人型】(代理人なしでの請求)など、多様化の傾向が見られます。
時効や制度変更が企業に与える影響
令和2年(2020年)4月1日の労働基準法改正により、残業代請求の時効期間が2年から5年に延長されました(労働基準法第115条)。ただし、当分の間は経過措置として「3年」とされています(労働基準法第143条)。この変更により、企業が負うリスクは従来の1.5倍(最終的には2.5倍)に拡大したことになります。
たとえば、従業員1人あたり年間約30万円(時給約1,100円、月20時間の残業を想定)の未払い残業代がある従業員が20名いる会社の場合、以前は最大1,200万円(30万円×20名×2年)だったリスクが、現在では1,800万円(30万円×20名×3年)にまで膨らみ(600万円の増加)、そして、経過措置が終了した場合には3,000万円(30万円×20名×5年)にまで膨らんでしまいます(1,800万円の増加)。そのため、残業代の未払いが発生しないような労務管理体制の構築は、もはや企業経営における必須事項といえるでしょう。さらに、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録保存義務も同じく、5年(当面の間「3年」)に延長されており(労働基準法第109条)、適切な記録管理がより一層重要になっています。
退職者から残業代請求をされた場合の対応手順
元従業員から残業代請求の内容証明郵便が届いた場合、決して無視してはいけませんが、慌てて対応してしまうと、本来支払う必要のない金額まで認めてしまう恐れがあります。ここでは、企業がとるべき対応の基本的な流れを4つのステップに分けてご紹介します。
1.請求内容が正当か、客観的証拠で事実確認を行う
退職者から残業代請求を受けた場合、まず重要なのは冷静に事実確認を行うことです。請求書に記載された労働時間や金額が本当に正確なのかを、客観的な証拠に基づいて検証する必要があります。具体的には、
- タイムカード(電子式を含む)
- 出勤簿
- PCのログイン・ログオフ記録
- 業務日報
- 入退館記録
- 電子メールの送信時刻
- 就業規則、賃金規程、雇用契約書
- 賃金台帳
など、会社が管理している記録を総合的に検討します。なぜなら、退職者が主張している労働時間には、実際には労働していない時間(休憩時間、私的な時間など)が含まれている可能性があるからです。また、労働者側の記録(手帳やメモなど)は主観的な要素が強く、裁判所でも客観性に疑問が持たれることが少なくありません。そのため、会社として保有している客観的な記録を基に、正確な労働実態を把握することが第一歩となります。
2.企業側として主張・反論できる点がないか検討する
事実確認を行った後は、企業側として法的に主張できる反論点がないかを検討します。主要な反論点としては、たとえば、次のような反論が考えられます。
- 固定残業代として既に支払っている
- 管理監督者であったため残業代は発生しない
- 実際の残業時間は請求よりも少ない
- 時効により請求権が消滅している
- 会社が明確に残業を禁止していた
ただし、これらの検討には専門的な法的知識が必要であり、また、それぞれの主張を裏付ける証拠の収集も重要になります。たとえば、固定残業代制度を採用している場合には、就業規則や雇用契約書の記載内容、実際の運用状況を詳細に確認し、制度の有効性を立証する必要があります。そのため、闇雲に反論するのではなく、勝算のある主張に絞り込んで、効果的な交渉を目指しましょう。これらの反論の具体的な内容については、後ほど詳しく解説します。
3.正確な未払い残業代を計算する
反論点の検討と並行して、仮に残業代の支払い義務があった場合の正確な金額を算出します。残業代の計算には、基礎単価の算定、除外賃金の確認、割増率の適用、既払い賃金の控除など、複数の要素を正確に把握する必要があります。特に注意すべきは、家族手当、通勤手当、住宅手当などの除外賃金が基礎単価に含まれていないか、また、固定残業代が既払い賃金として適切に控除されているかという点です。
さらに重要なのは、未払い残業代には本来支払われるべきだった日の翌日から遅延損害金が発生することです。この利率は、元従業員が退職済みの場合「年14.6%」(賃金の支払の確保等に関する法律第6条・同施行令第1条)という非常に高い利率が適用されるため、特に注意が必要です(在職中の場合は年3%《民法第404条》)。なお、退職金(退職手当)は「未払い賃金(残業代)」と異なり、民法や退職手当規定に基づく遅延損害金が適用されるのが通例となっています。そのため、請求対象期間が長期にわたる場合には、遅延損害金だけでも相当な金額になる可能性があります。
退職者側の計算では、これらの点が見落とされていることが多く、実際の支払い義務額よりも高額な請求となっているケースが散見されます。一方で、企業側としても遅延損害金の存在を軽視すると、最終的な解決金額が予想以上に膨らむリスクがあります。正確な計算を行うことで、交渉における適切な落としどころを見極めることが可能になります。
4.交渉と必要に応じた支払い
以上の検討を踏まえて、退職者側との交渉を行います。交渉においては、単に金額の減額を求めるだけでなく、法的根拠に基づいた合理的な主張を展開することが重要です。また、交渉が決裂した場合には労働審判や訴訟に発展する可能性もあるため、将来の手続きも見据えた戦略的なアプローチが求められます。なお、支払いを行う場合には、清算条項を含む合意書の作成が不可欠です。これにより、同じ問題で再度請求されるリスクを回避することができます。さらに、他の従業員への波及を防ぐため、守秘義務条項を設けることも検討すべきでしょう。
以上が、退職者から残業代請求を受けた場合に企業がとるべき基本的な対応手順です。
冷静に事実確認を行い、感情的に反応せず、「支払うべきものは支払い、支払わなくてよいものは明確に争う」という姿勢を示すことが大切です。
残業代請求への効果的な反論方法
消滅時効の援用
前述のとおり、残業代請求権には3年の時効があります。したがって、元従業員が3年以上前の期間を含む残業代を請求してきた場合、会社は「時効によりその部分の支払い義務は消滅している」と主張(これを「時効の援用」といいます。)することができます。ただし、時効の援用は明示的に行う必要があり、曖昧な表現では効力を発揮しません。そのため、内容証明郵便などで、どの期間の残業代について時効が成立しているのか、またその根拠を記載のうえ、「時効を援用する」旨の明確な意思表示をすることが重要です。また、残業代の支払い義務を認めるような発言や行動は必ず避けてください。「残業代は払いますから待ってください」といった発言は時効の承認とみなされ、時効期間がリセットされてしまう可能性があります。そのため、時効の援用を検討している場合には、初期対応から慎重に行うことが求められます。
労働時間性の否定(手待ち時間等)
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されており(三菱重工業長崎造船所事件《最高裁判所第一小法廷12年3月9日判決》)、単に会社にいた時間がすべて労働時間になるわけではありません。特に、手待ち時間や仮眠時間については、労働からの完全な解放が認められているかどうかが重要な判断要素となります。
三村運送事件(東京地方裁裁判所令和元年5月31日判決)では、重量のある医療用精密機械の運搬を行っていた運転手について、以下の事情などを総合的に考慮し、停車時間が労働時間に当たらないと判断されました。
- 労働協約や就業規則等を見ても貨物の常時監視を義務付けるような規定等がないこと
- 貨物は350kg以上あり、貨物のみの窃盗の可能性は高くないこと
- 有害・危険な毒劇物のような常時監視が必要な貨物ではないこと
- 積載貨物に保険がかけられていたこと
- 鍵を適切に管理していたにもかかわらず盗難があった場合には制裁を科す規定がなかったこと
- トラックから離れずに積載貨物を監視するように指示したことがなかったこと
- 休憩施設等において、睡眠・飲酒・入浴・食事などが運転手の裁量にゆだねられていたこと
- 取引先等からの問合せ対応なども恒常的に行っていたと認められないこと
このように、業務の性質や実際の拘束状況を詳細に検討することで、労働時間性を否定できる場合があります。
労働時間性の否定(自主的な自己研鑽時間)
従業員が業務時間外に行う研修や練習については、それが自主的な自己研鑽であるか、会社の指示による業務であるかが争点となります。この点が争われたルーチェ事件(東京地方裁判所令和2年9月17日判決)では、美容室のアシスタントが営業終了後に行う練習会について、労働時間該当性が否定されました。
|
【原告の主張(一部抜粋)】
➔ 練習会への参加時間は被告会社の指揮命令下にあった。 |
|
【裁判所の判断(一部抜粋)】
➔ 練習会は従業員の自主的な自己研さんの場という側面が強いものであったというべきである。 【裏付ける的確な証拠がなく、被告(会社・社長)の供述等に不自然、不合理な点は見当たらない】
➔ 指揮命令会に置かれていたと評価することはできない。 |
このように、研修や練習の任意性、個人的な利益の有無、業務上の必要性などを総合的に検討することで、労働時間性を否定できる可能性があります。
一方で、私見ですが、今回ご紹介した裁判例は「裏付ける的確な証拠がない」とされているので、練習会からの途中帰宅が許されていない・参加を命じられたことに対するメールやLINEのやりとりが提出されていれば、上記の事情があったとしても、労働時間該当性は認められていた可能性が高いのではないかと考えられます。
固定残業代制度の有効性の主張
固定残業代制度(みなし残業制)は、予め一定の残業代を基本給と分けて支給する制度ですが、制度設計に不備があると「有効な残業代の支払い」として認められません。
まず、固定残業代制度の有効性の判断には、日本ケミカル事件(最高裁判所第一小法廷平成30年7月19日判決)が参考になるので、ぜひ押さえておいてください。
この裁判では、業務手当が時間外労働等に対する賃金の支払と見ることができるかが争われました。裁判所は「時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき」と述べたうえで、「業務手当は、1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると、約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、…実際の時間外労働等の状況…と大きくかい離するものではない。これらによれば、…業務手当は、…時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められる」と判示しました。
固定残業代制度が有効と認められるためには、
①基本給部分と割増賃金部分の明確な区分
②時間外労働の対価としての性質
③予定時間数の合理性(※特に近時の裁判例)
などの要件を満たす必要があります。
①に関しては、日本ケミカル事件では、手当の金額は明示されていましたが、時間数の明示がなかったので、「時間数」「金額」のいずれかが明示されていれば認められる可能性はあります。
次に、②に関しては、手当の名称や支給条件から判断される場合があります。
たとえば、北港観光バス事件(大阪地方裁判所平成25年4月19日判決)では、「無苦情・無事故手当」は「バス乗務という責任ある専門的な職務に従事することへの対価」と判断されたり、日本コンベンションサービス事件(大阪高等裁判所平成12年6月30日判決)では、「会議手当」は「会議の時間等は要件となっておらず、…割増賃金の対象とはならない取締役等も支給の対象に含まれている。そうすると、これらが支給されるのは会議運営の困難さ等を考慮してのものと解され、時間外労働に対する割増賃金の正確を持つと考えるには疑問がある」と判断されたりするなど、固定残業代としては認められませんでした。
一方で、営業員の平均勤務時間を計測のうえ基本給の17%を定めた関西ソニー販売事件(大阪地方裁判所昭和63年10月26日判決)の「セールス手当」や、恒常的に深夜勤務を担う路線乗務員のみに支払われていた名鉄運輸割増賃金訴訟(名古屋地方裁判所平成3年9月6日判決)の「運行手当」は固定残業代として認められました。
こういった議論に晒されないためにも支給する手当の名称は「固定残業手当」などの名称にし、どういった者に対して支給するのかを定めておくことをおすすめします。
最後に、③に関して、あまりに長時間の残業(例えば月70超)を想定した固定残業代の定めは、公序良俗に反し無効と判断されるリスクがあります。たとえば、「時間外労働82時間相当分として支給」と採用条件通知書に記載していたビーエムホールディングス事件(東京地方裁判所平成29年5月31日判決)では「恒常的な長時間労働を是認する趣旨で、…手当の支払が合意されたとの事実を認めることは困難である。仮に、…合意をしたとしても、…公序良俗に反するものであり、無効と解するのが相当である…。したがって、…手当の全額が割増賃金の対価としての性格を有するという…主張は採用できない。」とられたり、「基本給23万円のうち8万8000円を月間80時間の時間外勤務に対する割増賃金とする旨が記載された本件雇用契約書を交付(昇給後に類似の別の規定あり。)」していたイクヌーザ事件(東京高等裁判所平成30年10月4日判決)では、「基本給のうちの一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは、…労働者の健康を損なう危険のあるものであり、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当」とされています。
これらの裁判例からみても、固定残業代制度を導入するのであれば、月30時間程度(多くとも月45時間)にしておくのが無難です。
管理監督者該当性の立証
労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合、残業代の支払い義務は発生しません(ただし、深夜労働に対する割増賃金は必要です。)。管理監督者の判断は、職務内容・権限・責任、勤務態様、賃金等の待遇を総合的に考慮して行われます。
管理監督者性の判断については、こちらの「残業代請求されないための雇用契約チェック【管理監督者性の判断基準】」で多数の裁判例と合わせて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
こちらでは最新の裁判例の自動車販売事業A社事件(岐阜地方裁判所令和6年8月8日判決)をご紹介します。この裁判では、中古車販売買取店の店長について、店舗の営業方法、買取金額、販売方法の決定権限、従業員の採否・シフト決定・労務管理権限などを有していたことから、「店舗の実質的経営者である」として管理監督者性を認めました。重要なのは、名目上の管理職ではなく、実態として経営者と一体的な立場にあるかどうかです。そのため、具体的な権限や責任の内容を詳細に立証することが必要になります。
残業禁止指示の立証
会社が明確に残業を禁止し、その指示が徹底されていた場合には、時間外労働の指示がなかったとして残業代の支払い義務を免れる可能性があります。ただし、単に「残業禁止」と言うだけでは不十分であり、業務量に見合った人員配置、具体的な業務改善措置、違反者への指導など、実効性のある取り組みが求められます。また、過度な残業禁止は「時短ハラスメント」としてパワーハラスメントに該当する可能性があるため注意が必要です。さらに、残業禁止にもかかわらず黙認していた場合には「黙示の残業指示」があったとみなされるリスクもあります。そのため、残業禁止の指示とその実効性について、客観的な証拠を整備しておくことが重要です。
残業代請求トラブルを弁護士に相談するメリット
元従業員からの残業代請求は、労務問題であると同時に、法的紛争の入り口でもあります。対応を誤れば、多額の支払いを命じられるだけでなく、他の従業員へ波及するリスクもあります。このような複雑な問題に直面した際には、早期に弁護士へ相談することが極めて重要です。
専門的な法的判断と交渉・和解のノウハウ
残業代請求への対応には、労働基準法、労働契約法、民法など複数の法律知識が必要であり、さらに最新の判例動向も把握しておく必要があります。特に、労働時間性の判断、固定残業代制度の有効性、管理監督者該当性などは、事案ごとに個別具体的な検討が必要な複雑な論点です。弁護士に相談することで、これらの法的論点について専門的な分析を受けることができ、企業にとって最も有利な主張を構築することが可能になります。また、労働者側代理人との交渉においても、法的根拠に基づいた説得力のある主張を展開することで、有利な条件での和解を実現できる可能性が高まります。
労務リスク予防体制の構築
残業代請求への対応は、目の前の問題解決だけでなく、将来的なリスク予防の観点からも重要です。弁護士に相談することで、現在の労務管理体制の問題点を洗い出し、未払い残業代が発生しない仕組みづくりを進めることができます。具体的には、就業規則の見直し、労働時間管理システムの改善、固定残業代制度の適正化、管理監督者の要件整理などが挙げられます。また、労働時間の上限規制強化、同一労働同一賃金の導入など、労働関係法令の改正動向にも対応する必要があります。継続的な法的サポートを受けることで、コンプライアンス体制の強化と企業リスクの最小化を図ることができます。
虎ノ門法律経済事務所における残業代請求対応サポート
交渉・労働審判・訴訟の対応
当事務所では、退職者からの残業代請求に対して、初期の交渉段階から労働審判、訴訟まで一貫したサポートを提供しています。まず、ご相談いただいた段階で、事案の詳細な分析と法的リスクの評価を行い、お客様の意向と法的リスクをバランスよく踏まえた対応戦略をご提案いたします。交渉においては、企業側の立場を最大限に活かした主張を展開し、可能な限り有利な条件での解決を目指します。また、交渉が決裂し労働審判や訴訟に発展した場合にも、豊富な経験と専門知識を活かして、企業の利益を守るための最適な訴訟戦略を構築いたします。弁護士が対応することで、感情的な対立を防ぐことができ、冷静かつ戦略的な判断が可能になります。
労務管理体制のコンサルティング
残業代請求への対処だけでなく、根本的な労務管理体制の改善についてもサポートいたします。当事務所では、企業の業種・規模・特性に応じた労務管理体制の構築をお手伝いしており、就業規則の策定・改定、労働時間管理制度の設計、固定残業代制度の適正化などを総合的にサポートしています。また、管理監督者の要件整理、36協定の適切な締結、労働時間記録の管理方法など、実務に直結するアドバイスも提供いたします。さらに、労働関係法令の改正動向についても継続的な情報提供を行い、常に最新のコンプライアンス要求に対応できる体制づくりをサポートしています。
継続的なサポートと情報提供
当事務所では、残業代請求をはじめとする多様化する労働問題に対応するため、企業向けの勉強会・セミナーを定期開催しております。顧問先企業様は、セミナーへの参加費が無料となっており、後日のアーカイブ動画配信サービスも行っております。実際に、今回のテーマである「残業代請求への対応」についても専門的な勉強会を実施済みで、アーカイブ動画をご提供しています。社会保険労務士向けの内容ではありますが、経営者の皆様にも十分参考になる実践的な内容となっております。
まとめ
退職者からの残業代請求は、適切な初期対応と法的知識に基づく戦略的なアプローチが解決の鍵となります。まず、冷静に事実確認を行い、客観的な証拠に基づいて労働時間の実態を把握することが重要です。そのうえで、消滅時効の援用、労働時間性の否定、固定残業代制度の有効性、管理監督者該当性など、企業側として主張できる反論点を専門的に検討する必要があります。
しかし、これらの判断には高度な法的専門知識と豊富な実務経験が不可欠です。感情的な対応や安易な妥協は、かえって企業のリスクを拡大させる可能性があります。また、目の前の問題解決だけでなく、将来的な労務リスクを予防する体制構築も同時に進めることで、企業の持続的な成長を支えることができます。
退職者からの残業代請求でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ